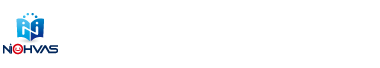大宮東口校 からのお知らせ:
焦りやイライラから抜け出せ! 不安解消・ストレス解消方法5選
こんにちは、個別指導塾ノーバス大宮東口校専任講師の笠木です。
不安な気持ちを解消できず、毎日の勉強や仕事が手につかない……というのは、誰にでも起こることです。
将来の生活やキャリアが不安会社でのプレゼンテーションが成功するか不安わけもなく、漠然とした不安を感じるどこか落ち着かず、焦りを感じるなど、人によってさまざまな不安があるでしょう。そんなときは、今回ご紹介する5つの方法をお試しあれ。不安を解消し、仕事や勉強に必要な集中力を取り戻せるはずです。
不安を解消する方法を学ぶ前に、精神的不安が生じる原因を理解しておきましょう。
厚生労働省の「みんなのメンタルヘルス総合サイト」によると、不安や緊張の原因のひとつは「心配事」。
来週のプレゼンテーションは成功するだろうか資格試験に合格できるだろうか理想通りのキャリアを築けるだろうか大災害が起こらないだろうか人間ドックの結果が悪くないだろうか
という具合に、不確定な未来について心配すれば、不安が生じるのは自然なことです。このように「正常な不安」は、危険に備え、問題を解決するために必要なものだそうですよ。
メンタリストDaiGo氏は、不安の原因のひとつとして「ネガティブバイアス」を挙げています。ネガティブバイアスとは、ポジティブなことよりネガティブなことに反応してしまう、思考のクセです。
たとえば、「上司が笑った」という事象について。「ほほ笑んだ」とポジティブに解釈する人もいれば、「苦笑」ととらえて不安になってしまう人もいるでしょう。後者のように何事も悲観的に解釈するのが、「ネガティブバイアスが強い人」です。
◆ネガティブバイアスが強い人は……
上司の笑顔を「苦笑」と解釈
→不安を抱きやすい
◆ネガティブバイアスが弱い人は……
上司の笑顔を「ほほ笑み」と解釈
→不安を抱きにくい
ネガティブバイアスが強い人は、不安のために集中力が低下しがち。中国科学院による2016年の研究では、ネガティブバイアスが強い人ほど自動車事故を起こしやすいと示されています。
身体のコンディションが悪いときも、不安やイライラなどのネガティブ感情が生まれやすいもの。自律神経やホルモンバランスが乱れると、精神に悪影響が及びます。不安を遠ざけるには、健康的な生活習慣を心がけ、ストレスや疲れをため込まないのが大切です(詳しくは後述)。
◆体調不良の原因
食生活の乱れ睡眠不足運動不足疲労・ストレスの蓄積 など
精神的な病
不安感があまりに強いなら、精神的な病が原因かもしれません。前出の「みんなのメンタルヘルス総合サイト」によると、不安が主な症状として現れる精神疾患は「不安障害」と呼ばれ、「パニック障害」や「全般性不安障害」などがあるそうです。
精神科医の信田広晶氏によると、以下の状態に当てはまるなら、心療内科か精神科を受診するべきだそう。
特に原因がないのに、長期間にわたり強い不安を感じているありえない出来事を想定し、過剰な不安を感じている日常生活に悪影響が及んでいるほどに不安感が強い【例】外出できない、仕事や家事ができない、乗り物に乗れない精神的苦痛を感じるほど、不安感が強い自分の気持ちをコントロールできない
不安感があまりに強く、自力で解消できそうにない場合、お医者さんの力を借りましょう。
不安を解消する方法1:解決行動をとる
不安が具体的で、それほど強くないなら、自分でできる解消方法を試してみましょう。最もシンプルな解消法は、不安の原因を取り除く行動をとることです。
精神科医の樺沢紫苑氏によれば、私たちが不安を感じるとき、脳内で「ノルアドレナリン」という神経伝達物質が分泌されているそう。ノルアドレナリンには、ピンチになったときに「戦う」「逃げる」などの行動を急かす役割があります。不安は「さっさと動かないとまずいぞ!」という脳からのシグナルであり、行動のエネルギーなのです。
不安を感じるときは、行動を起こすべきとき。解決行動をとれば、ピンチを脱出でき、不安が解消されるはずです。
◆ピンチから脱出する例
プレゼンテーションが成功するか不安→成功を確信できるくらい、準備を完璧にする資格試験に合格できるか不安
→合格を確信できるくらい、勉強を頑張る今後のキャリアが不安
→具体的なキャリアプランを立てる、先輩や上司に相談する災害が起きないか不安
→防災グッズを買う、災害時の動きをシミュレーションする
不安の原因がハッキリしているなら、とにかく行動を起こし、問題を解消しましょう。
不安を解消する方法2:脱フュージョン
不安を解消するには、メンタリストDaiGo氏が紹介する「脱フュージョン」がいいでしょう。ごちゃごちゃに混ざった感情から、ネガティブな考えを切り離す方法です。不安の原因のひとつ「ネガティブバイアス」を弱められますよ。
脱フュージョンにはさまざまなやり方があり、DaiGo氏は以下の4つを挙げています。
1つめは、不安の大きさを点数化する方法。最悪の不安感情を「100」とし、いま抱えている不安がどの程度か、数字にしてみましょう。
強盗に銃を突きつけられているときの不安:100プレゼンテーションを控えているときの不安:60試験に合格できる自信がないときの不安:50こんな具合に点数化し、不安を客観視することで、ネガティブバイアスが弱まっていきます。
2つめは、歌唱法。「プレ~ゼン~が心配だ~♪」「試験に~落ちたら~どうしよう~♪」という感じに、不安な考えや感情をメロディーに乗せて吐き出す方法です。不安を歌にすることで、「そんなに深刻な事態ではないな」と思え、ネガティブバイアスが弱まります。また、歌のバカバカしさから、不安感を笑い飛ばすこともできるのです。
不安感情を「擬人化」するのも有効。
「“不安くん” が心のなかで暴れているな」
「“不安ちゃん” が今日も元気だな」
という具合に考えると、不安を「自分とは別の生き物」として切り離しやすくなります。
4つめは「列車法」。あなたは駅のホームに立っています。そこに貨物列車が走ってきました。貨物列車にネガティブな感情をどんどん放り込んで、そのまま走り去るのを見送ってください。
このようにイメージするのが、列車法。「痛いの痛いの飛んでいけ」のように、ネガティブなものを自分から切り離せますよ。
自分に合う「脱フュージョン」をやってみてください。ネガティブバイアスが弱まり、不安の解消につながります。
不安を解消する方法3:生活習慣を見直す
不安を解消するには、生活習慣の改善も有効です。
「心配事などないはずなのに、漠然とした不安を感じる」
「些細なことを気にしすぎてしまう」
こんな方は、生活習慣の乱れやストレスにより、心が不安定になっているのかも。生活習慣を見直すことで、不安が収まる可能性があります。前出の信田氏によると、不安障害を生むストレスや疲労を解消するには、以下のことを意識するのがいいそうです。
起床・就寝の時刻を一定にする食事の時刻を一定にする朝食をしっかりとる1日20~30分程度、軽い運動をする【例】ストレッチ、ウォーキング、ヨガ40度くらいのぬるめの湯船に浸かるリラックスできることをする
【例】マッサージに行く、アロマをかぐ、お茶を飲むよく笑う暴飲暴食をしないお酒やコーヒーを飲みすぎない
基本的なことばかりですが、ストレス解消・不安解消のため、ぜひ実践してみてください。
不安を解消する方法4:食生活を見直す
不安を解消するため、食事にも気を配りましょう。心療内科医の姫野友美氏、精神科医の奥平智之氏らの見解を参考に、3つのポイントをご紹介します。
タンパク質をとる
姫野氏によると、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンは、タンパク質を材料とします。不安を感じている方は、タンパク質が足りず、セロトニンが不十分なのかもしれません。
肉・魚・卵・乳製品などに含まれる動物性タンパク質だけでなく、大豆などの植物性タンパク質も摂取するのがコツだそう。タンパク質が分解されてできるアミノ酸のバランスがよくなるそうですよ。
鉄分をとる
奥平氏によると、セロトニンをつくるには鉄分も必要。鉄分が不足すると、イライラや不安などの症状につながるそうです。
鉄分が豊富な食品は、赤身の肉や魚。タンパク質も多く含まれているので、不安を感じているときは積極的に食べましょう。
糖分は控えめに
摂取を控えるべきなのが、糖分です。姫野氏によれば、糖分ばかり摂取すると血糖値が激しく上下し、気持ちが不安定になるのだとか。お腹いっぱい食事をしたあとに眠くなったり、集中できなくなったりするのは、このためです。
リフレッシュのために甘いものを食べる方は多いかもしれませんが、逆効果になるリスクも。スイーツのみならず、米や麺類などにも糖分が多いので、不安感に苦しんでいるときは食べすぎないことをおすすめします。
以上が、食生活で気をつけたい3つのポイント。もちろん、タンパク質や鉄分以外の栄養も、バランスよく取り入れることが大切。不安を解消するには、食生活を見直してみましょう。
不安を解消する方法5:呼吸法
不安を解消するには、自律神経のバランスを整えるのが有効です。順天堂大学医学部教授でスポーツドクターの小林弘幸氏によると、「6秒吐いて、3秒吸う」呼吸法で、自律神経が整うそうですよ。
自律神経は、脈拍・体温調節・消化・呼吸・免疫機能など、全身に関わっています。そのため、自律神経の乱れは、身体や心の不調につながるのです。
自律神経が集まっているのが、腹式呼吸のときに動く「横隔膜」という筋肉のまわり。小林氏によれば、ゆっくり深く呼吸すると、横隔膜が大きく動いて自律神経が刺激され、整うそうです。
小林氏が推奨する「自律神経を整える呼吸法」のやり方は、以下のとおり。
足を肩幅に開き、まっすぐ立つ両手を脇腹に添える上体を前に軽く倒しながら、6秒かけて息を吐く息を吐きながら、脇腹の肉をへそに集めるようにして、腸を刺激する背中をそらしながら、3秒かけて息を吸う。手の力は緩めていく
以下のようにアレンジすれば、リラックス効果が高まるそうです。
足を肩幅に開き、まっすぐ立つ全身をできるだけ上に伸ばす両腕を上げ、右手のひらと左手の甲を重ねる脱力し、6秒かけて息を吐くもとの姿勢に戻り、3秒かけて息を吸う
この呼吸法を1~3分間続ければ、自律神経が整ってリラックスできるそう。不安感を解消したいときは、ぜひ試してみてください。
不安を解消する言葉
最後に、不安の解消につながる言葉をご紹介します。3人の著名人による名言です。
〇松下幸之助の名言
失敗すればやり直せばいい。
やり直してダメなら、もう一度工夫し、もう一度やり直せばいい。
パナソニックの創業者・松下幸之助氏の名言。仕事や試験など、未来のことが不安でどうしようもなくなったとき、この言葉を思い浮かべてみてください。
「たとえ失敗しても、そこから学んでやり直せばいいだけ」。そう考えれば、どんなことも恐れず、前向きにチャレンジできるはずです。
〇坂本龍馬の名言
世の人は われをなにとも ゆはばいえ わがなすことは われのみぞしる
幕末の志士・坂本龍馬の言葉。「世間にどう批判されてもかまわない。私がやることの意義は、私だけが知っているのだから」という意味です。
何かに挑戦したり、信念を貫こうとしたりする人は、批判されることもしばしば。そんなときはこの名言を思い出し、坂本龍馬の生き様から、前へ進んでいく勇気をもらいましょう。
〇高村光太郎の名言
僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる
詩人・高村光太郎の詩『道程』の一節。中学校の国語の教科書に載っているので、ご存じかもしれません。
人生では、「前例がないこと」に挑む場面もありますね。そんなときに唱えたいのが、この言葉。誰かが通った道をなぞるのではなく、新しい道を切りひらいていくんだ! ――そんな気概が生まれ、チャレンジへの不安が解消されるはずです。
なかなか不安を解消できないときは、脱フュージョンによって客観的になるだけでなく、生活習慣や食生活を見直しましょう。不安を抱えている方は、ご紹介した解消法を、ぜひ実践してみてくださいね。
ノーバスでは、授業含め、各教科ごとに生徒に合った勉強法を講師陣がアドバイスしています。
無料カウンセリング・体験授業は下記までお問い合わせください。
http://www.nohvas-juku.com/cs/cs_taiken.php
TEL:048-729-6515
MAIL:omiyahigashi@nohvas-juku.com
[2021-12-06]