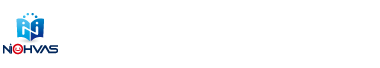がんばる先生の指導ノート
ノーバスでがんばる先生が
生徒への想いや、勉強のこと、出来事など
教室の日常をお届けします。
みなさんこんにちは。
個別指導塾ノーバスです。
生物の勉強の仕方に迷いはないでしょうか。
今回は、生物勉強の仕方についてクローズアップしていきます。
🧬生物の勉強が大変な理由(高校〜大学受験レベル)
①覚える量がとにかく多い
生物は、専門用語・現象名・構造名など、暗記すべき言葉が圧倒的に多いです。
たとえば「細胞の構造」だけでも
👉 ミトコンドリア・リボソーム・ゴルジ体・リソソーム…など数十個。
さらに、それぞれの働き・構造・関連する反応まで理解する必要があります。
つまり、ただ単語を覚えるだけでなく
「どのしくみで何が起きるのか」を“関連づけて”覚えないといけないのが大変なポイントです。
②図やプロセスを「イメージ」で理解する必要がある
生物は、教科書の中で図や流れの理解が命です。
たとえば、
光合成の反応経路
DNA → RNA → タンパク質への転写・翻訳の流れ
ホルモンの分泌とフィードバック調節
など、**「順番」「場所」「はたらき」**の3つを同時に整理する必要があります。
一つでも抜けると、全体の仕組みがわからなくなってしまうんです。
図を「写すだけ」ではなく、「自分で描けるようになる」まで理解することが大切です。
③“暗記だけ”では点が取れない
特に大学入試では、説明問題や実験考察問題が多く出題されます。
知識を丸暗記しても、「なぜそうなるのか」「他の条件ではどうなるのか」と問われると答えられない。
つまり、「理解+応用」が求められるのが生物の難しさです。
例:
光合成の反応がどんな条件で止まるかを説明せよ。
単なる暗記ではなく、「光エネルギー → ATP生成 → カルビン回路」という流れを理解していないと解けません。
④似た用語が多くて混乱しやすい
生物では、似た名前の用語や構造が多く出てきます。
たとえば:
DNAポリメラーゼ と RNAポリメラーゼ
交感神経 と 副交感神経
減数分裂第Ⅰ分裂 と 第Ⅱ分裂
こうした言葉を“なんとなく”で覚えると、問題で間違いやすくなります。
整理ノートを作る・図にまとめるなどの工夫が必要です。
⑤出題範囲が広く、積み上げが必要
生物は「生物基礎」で終わらず、「生物」ではさらに
進化・生態・遺伝子・代謝などが深く学び直されます。
つまり、基礎の理解が甘いと上の内容がまったく入ってこないという構造です。
たとえば「DNAのしくみ」を理解していないと、
「遺伝情報の発現」「バイオテクノロジー」の内容が理解できません。
🔍まとめ
生物が大変なのは、
覚える量が多く
流れと仕組みの理解が必要で
暗記だけでは点にならず
似た用語が多く
基礎が積み重なっていく
からです。
でも逆に言えば、理解を丁寧に積み重ねれば着実に伸びる科目でもあります。
特に図やプロセスを「自分の言葉とイメージ」で説明できるようになると、生物は一気に楽しくなります🌿